本プログラムを通じて養成すべき人材像
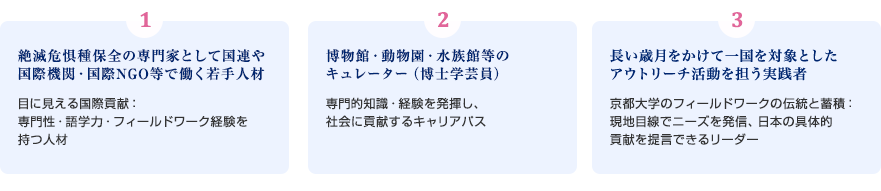
1. 絶滅危惧種保全の専門家として国連や国際機関・国際NGO等で働く若手人材
目に見える国際貢献:専門性・語学力・フィールドワーク経験を持つ人材を輩出日本は国際連合(UN)の主要なドナー国でありながら、職員数は著しく少ない。国連機関で働く、博士学位をもった、外国語に堪能で発信能力に優れた人材を養成する必要がある。また欧米には、IUCN(国際自然保護連合)、WWF(世界自然保護基金)、この2団体が共同で設立したTRAFFIC(トラフィック)や、WCS(野生生物保護協会)、FFI(ファウナ・アンド・フローラ・インターナショナル)、CI(コンサベーションインターナショナル)など、歴史と伝統をもった巨大なNGO 組織がある。それが国連のUNEP(国際連合環境計画)、UNICEF(国際連合児童基金)等の補助機関、 世界銀行、UNESCO(国際連合教育科学文化機関)等の専門機関等と連携している。日本の国際機関に対する経費拠出に比して、国連職員はきわめて少なく、また国際NGO 組織の受け皿も少ないのは、そうした国連機関や国際NGO等で働ける専門性と語学力とフィールドワークの現場経験をあわせもった人材が乏しいことが大きい。本プログラムを通じて、そういった組織運営の現場経験をもちフィールドワークの学位を有するリーダーを育成することが、国際社会の一員としての日本の急務である。幸い、これまでに先端研究拠点事業やITP やJST-JICA のSATREPS等で、日独米英仏伊の先進6か国連携体制を確立し、生息地の主要研究機関とも覚書を通じた連携体制を構築してきた。それをもとに、ワイルドライフサイエンスの研究能力を持ち牽引力のある国際的実践者としての人材育成をめざす。
2. 博物館・動物園・水族館等で活躍するキュレーター
専門的知識・経験を発揮し、社会に貢献するキャリアパス日本動物園水族館協会JAZAには約90 の動物園と70 の水族館が加盟している。これらは、法令上は博物館等みなし施設である。欧米ではリサーチフェローやキュレーター等の職が確立していて、博士学位をもった人材が、研究と教育を両立させつつ園館の運営等に深く関わっている。しかし、日本では野生動物を対象にしたフィールドワークを基盤に、人間とそれ以外の動物との調和ある共存について学問と実践を統合する人材がきわめて乏しい。とくに動物園・水族館・博物館の約3分の2は地方公共団体が直接・間接に経営に関与しているので、地方公共団体など行政との連携も不可欠である。また、絶滅危惧種が多く、それらについては国際連携が不可欠で世界動物園水族館協会もあるが、日本の存在感はきわめて乏しい。動物園・水族館等を舞台にして国際的な情報発信とコミュニケーションを担える主事の役割を果たす人材を育成する必要がある。その先に、国内外の生息地そのもので展開する新しい動物園博物館としての「フィールドミュージアム」の実現をめざす。そのためには実体験を下敷きにして学問成果を伝えられる学位をもった科学コミュニケーターのような職種もきわめて重要である。法令によって定められた博物館の学芸員資格だけではなく、さらに一歩進めて、真に科学を学んだ博士学位取得者が、博物館等での活動を通じて科学の研究成果を、わかりやすく的確に専門知識を持たない人たちに伝えることができるようにしたい。
3. 長い歳月をかけて一国を対象としたアウトリーチ活動を担う実践者
京都大学のフィールドワークの伝統と蓄積:現地目線でニーズを発信、日本の具体的貢献を提言できるリーダーを輩出京都大学は、近年、全学を挙げて1 国を対象としたアウトリーチ活動をおこなってきた。最初の対象はブータンである。1957 年以来の半世紀を越える縁があり、過去2 年半のあいだに11 次79 名の訪問団と2 次12 名の受け入れをおこなってきた。京都大学のフィールドワークの伝統を活かしたユニークなプログラムになっている。近年の相互交流は、フィールド医学を柱にした地域に根ざした医療の実践から始まり、同国初の医科大学ならびに医学部の創設に向けて京都大学としての貢献を実践している。こうした基盤には、総合大学としての、文化・教育・宗教・防災・生物・農業・環境等についての広範な協力体制が必要だ。ブータンにおけるこの1国まるごとを対象としたアウトリーチ活動の実践は、グローバル人材育成のロールモデルになるだろう。本プログラムでは、ゲノム科学から行動学や生態学まで、フィールドワークを基本とした手法で、生物多様性のホットスポットにおける生物保全活動を目指している。次なる展開としては、アマゾン(ブラジル)、ボルネオ(マレーシア)、中国・雲南省、インド、アフリカ(東部のタンザニア・ウガンダ、中部のコンゴ・ガボン、西部のギニア・ガーナ)といった国と地域がある。そこでは、具体的構想や貢献を一国の政策として実現していく手腕をもった人材が必要となる。長い歳月をかけて1 国を対象としたアウトリーチ活動を担える、オールラウンドな指導者となる人材を育成する。